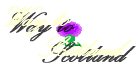Scotch Whisky History
スマグラーの時代
ウィスキーの製造についてはアイルランド発祥説とスコットランド発祥説があるがどちらが正しいのかは定かではない。 16世紀には既にスコットランドでウィスキーの生産が行われていた。その時代はほとんどが地元に供給される小作地や農場を中心に構成されるとても小規模な家内工業的産業だった。 蒸留は生まれながら持っている権利と考えられていた。
1644年にスコットランド議会は初めて酒に税金を課した。酒は最初の間接課税のしくみのための実験材料になった。 しかし、その当時の人々は税金を払うことを嫌がった。その中でも特に酒に課せられた税金は嫌がった。 そしていろいろな方法で税金を払わないことは、国民の楽しみとなった。娯楽の少ない時代の一種のゲームのようなものだったのかもしれない。
1707年のイングランドとの連合(併合)の後の新しい United Kingdam で、特に酒とたばこの税金が上乗せされた税法が作られた。
しかしこの時アイラ島が何らかの不手際からこの税法が適用されないこととなった。そこの地主は確実な収入源としてウィスキー蒸留を奨励した。 幸いにも島には豊富にコケを含んだピートとピートが溶け込んだ川がある。そしてアイラ島は一段と優れたウィスキーの島となり、今に至る。
1707年からおよそ120年間、政府は成長する蒸留業者に、不法蒸留や密造することをやめさせようといろいろと試みた。 蒸留酒の税金は年々上下した。またその産地(イングランド・スコットランド・アイルランド)によっても条件が変わった。
1784年の改定ではスコットランドの、GreenockとDundeeの間に引かれるローランドとハイランドの境界線"Highland Line"を設け、 ハイランドの課税が強化された。
1786年の改定では販売がライセンス制となり、イングランドの商人にウィスキーを売るライセンスを持っていたのは一握りでしかなかった。 さらにハイランドの蒸留業者はローランドにすら売ることが出来なかった。さらにイングランドへ売る場合には課税された。
また、今までウォッシュの生産量を基準に課税されていたのがスティルの容量に基づいて課税されるようになった。 徴収される法外な税金のため、合法的な蒸留所では浅く低容量のスティルで何回も蒸留を繰り返す(一時間に4回ぐらい)製造手段が定着した。 その結果は下品な味のウィスキーと焦げて不衛生なスティルであった。
こういった状況から、ハイランドでは密造が盛んになった。峡谷が多く隠れる場所には不自由しなかったのも要因の1つだろう。 一方、都市部のローランドでは合法的な蒸留所が中心だった。しかし高い税金のため、生産コストを下げないと商売にはならない。 浅いポットスティルはローランドに多かった。
高くてまずい正当な酒と安くておいしい密造酒とではどちらが売れるのかはいうまでもない。スコッチウィスキーの主流は密造酒となった。
役人でさえも密造酒を飲んでいた。人気のある不法蒸留所ではウィスキーがすべて政治家や役人に確保されるので一般の人々には手に入らないということもあった。
1822年、当時の国王ジョージ4世がスコットランドを訪問した際、Glenlivetを所望したのは有名な話。国王自ら密造酒を認めていたことになる。
さらに悪いことにスコットランドは1790年代から1810年頃まで、悪天候と凶作に苦しめられた。政府は醸造や蒸留のための大麦の使用を禁止する必要があった。すべての穀物は、人間が必要とした。しかしその時代ですら不法な蒸留はされていた。特にハイランド、および周辺諸島、そしてアイルランドで多く行われていた。イングランドへの反抗を秘めた誇り高き闘いでもあった。
密造者と徴税官との戦いは数々の逸話を生み出した。お互い知力を尽くして相手を欺こうとした。
その当時農民の生活は厳しく、とても貧しかった。ウィスキー蒸留は生活のための重要な現金収入源だった。
一方で徴税官の暮らしも豊かではなかった。収入は逮捕して徴収できた罰金の額に比例して払われた。 しかし刑を決定する地元の判事はその地域の地主ということが多かった。密造者はその地主から原料の大麦を購入する、 出来上がったウィスキーを地主が飲んでいる、というわけで公平な判決が下されるわけがなく、 罰金は最低限に押さえられた。当然、徴税官の収入は減る。 しかも逮捕にかかる費用は自分持ちだったという。
産業としての確立
密造者と徴税官との戦いは1820年代まで続いた。そして1823年の有名な税法改正と1846年の穀物条例の廃止によりUKのウィスキー産業の様子が変化した。
前者の法令はUKで初めての合法的にウィスキーを製造するための現実的なものだった。後者は穀物の収穫高の税金を事実上廃止した。 そして外国、特に北アメリカからの大麦や穀物の輸入を自由にした。
その結果、無数の人々が蒸留業者として登録することとなった。多くの蒸留業者や密造者も含まれる。 しかし不法蒸留は減少したがハイランドで19世紀末まで続けられたらしい。1820年代、ウィスキー蒸留は一攫千金目当ての産業となった。 何百という会社が設立されたがほとんどはつぶれていった。
農場主にとってはウィスキー製造に参入することは自然な流れだった。多くは敷地内によい水源を持っていた。ピートの産地が近くにあった。そして利用できる建物があった。その周辺にはウィスキーが消費されるであろう市場が整っていた。ウィスキー造りは穀物を製粉所や他の小売店に売るより、はるかによい投資の見返りがあった。
しかしながら、現実はそれほど簡単なものではなかった。
大部分の新しい蒸留所は小さく、2つのポットスティル、農場の建物を流用して蒸留所を開業した。少数の蒸留所は地元の資産家などから財政的支援があった。さらに1700年代中期から操業しているLowlandのいくつかの大きな蒸留所があった。また、この時期に蒸留所を建て直して規模を拡張した蒸留所もあった。しかしほとんどの小規模な蒸留所の経営は厳しかった。ブームが終わり、生き残った蒸留所は19世紀の終わりまでまたそれ以降も順調に操業していった。
スコッチウィスキーを発展させた要素の1つに産業革命があった。これにより、はるかに大きい銅のスティルを妥当なコストで製造することが可能になった。
大きなボイラーはモルトから糖分を抽出するための十分なお湯やスティルを熱するための蒸気を供給することができた。
鉄道と船によって大量輸送が可能になり、大麦や燃料など原料の供給が安定するようになった。そして生産されたウィスキーも遠方の顧客や消費者に輸送することが可能になった。
もちろん、すべてこれは短期間で起こったことではない。この頃はほとんどの蒸留所はウィスキーを樽で地元のパブや酒店に売っていた。町の酒店は4,5樽の異なる地元のモルトウィスキーをストックしていただろう。消費者は容器を持って来て、樽から直接満たしていた。この方法は世界のいろいろな場所で見られる。
19世紀の成長期の活発な時期に、ウィスキー蒸留はビール醸造と非常に関係が深かった。ビール醸造所から発展した蒸留所もいくつかあった。モルティング〜発酵までの工程はほぼ同じなので施設の流用が可能だったと推測される。この時代の古い写真には蒸留所のモルトキルンにまだビール醸造所の名残が見られることもある。
蒸留所の象徴とも言えるパゴダ屋根のあるモルトキルンは1889年、Dailuaine蒸留所の拡張時に建築家のCharles Chree Doigによってデザインされたのが最初とされている。以降、彼のデザインした蒸留所にはすべて取り入れられている。
なお、後年、蒸留所として閉鎖された後、ビール醸造所として再出発した施設もあり、ウィスキーとビールの関係は深い。
黄金の時代
産業革命と輸送手段の進歩がウィスキー産業の成長に重要な役割を果たしてきた。加えて4つの幸運な出来事がさらにウィスキー産業の成長に寄与した。パテントスティルの発明、フランスのブドウ園を荒廃させたフィロキセラによる大きな虫害、安いガラスビンの大量生産、そしてブレンデッドウィスキーという発想である。
コフィースティルの発明者、Aeneas Coffeyは1820年代、アイルランドのダブリンで税務官の職に就いていた。彼はその時代の一般的なポットスティルの作業がとても効率が悪いことに気づいていた。ポットスティルは蒸留後、冷めるまで待って中を清掃してからでないと次の蒸留は行えない。したがって実際に蒸留をしている以外の時間が多くかかった。 Coffeyは1830年に特許を取った。そのスティルは大きく、複雑な装置だった。パテントスティルはポットスティルより能率的で、不純物の少ないアルコールの生産が可能、そしてメンテナンスや通常の清掃の必要なしに一日中稼働することができた。
欠点は高い初期コスト、出来上がったウィスキーは特色と香りに乏しい、そして長く稼働しなければ利益が上がらないことだった。これは小さい地方の蒸留所で操業するのをとても難しくした。その結果、パテントスティルにとって必要なウォッシュの量を生産することができた、大きな都市部の蒸留所が最初に採用した。Lowlandにグレーン蒸留所が多いのはこういった理由からである。
さらに、大きなスティルを満たすために必要なモルトの量を見極めるのが難しかった。これを解決したのがアメリカから来たトウモロコシだった。トウモロコシはアメリカ人が彼らの蒸留所のための安い原材料として使い始めた。彼らはトウモロコシを、蒸気で柔らかく調理し、それからモルティングされた大麦と4:1の比率で混合し、パテントスティルに最適なウォッシュを生産した。
トウモロコシ80%と大麦20%をベースとしたウィスキーは大きな都市部の蒸留所の主要生産品となった。グレーンウィスキーと呼ばれたそれはモルトウィスキーの影を薄くするようになった。それははるかに安く、よりなめらかで、多くのモルトウィスキーの品質が年々、また蒸留所ごとに変化したその時代に、安定した製品を造ることが可能だった。 ローランドはグレーンウィスキーが主流となった。生産量は増加し、19世紀末にはモルトウィスキーを上回った。
また、グレーンウィスキー蒸留所はウィスキー生産だけではなかった。グレーンウィスキーの再蒸留によってジンの材料に最適な安いスピリッツを生産することができた。
ジンはこの時代に人気のあったオランダの蒸留酒をコピーしたもので、すぐに酔っぱらい、しかも安い。都市部のダウンタウンの安酒場で1ジル(1/3パイント)1ペニーだった。とても広く普及した飲み物で特に労働者階級の女性の間で広まった。ジンが「母親の破滅」のニックネームをつけられたことは笑ってすませられることではなかった。
スコッチウィスキー産業の成長は新たに、UKや海外にウィスキーや他の酒を大量に売りさばく、ウィスキー業者を作り出した。多くの業者はウィスキーの特徴と欠点に気づいていた。グレーンウィスキーはなめらかだが単調すぎる。モルトウィスキーは個性的だが品質が一定ではない。これらの解決策がグレーンウィスキーとモルトウィスキーの良さを兼ね備えるブレンデッドウィスキーだった。このウィスキーを瓶詰めしてラベルを貼って商品化したのが Andrew Usher が最初とされる。
この時代以降、スコッチウィスキーの主流は徐々にブレンデッドウィスキーとなる。ビッグ5と呼ばれるメーカーもこの頃に生まれた。
19世紀中期のUKの蒸留酒マーケットは不思議な階層に分かれていた。上流階級はブランデーを飲んでいた。労働者階級はジンを飲んでいた。海軍ゆかりの町ではラムが人気があった。ウィスキーはスコットランドの地酒として、地元で消費されるのが中心だった。ウィスキーに特に問題があるわけではなかった。
しかし1890年代に入るとウィスキーを取り巻く環境が一変した。皮肉にも国外の不幸がその変化を起こす引き金となった。フランスのブドウ園を荒廃させた、ごく小さい害虫、フィロキセラだった。
フィロキセラは植物の茎から樹液を吸って生きている。吸う時に、ごくわずかな量の唾液を植物に注入する。フランスのブドウはこれに免疫が無いため、枯れて死んでいった。 フィロキセラはフランスを破滅的な結果にした。正確な数字は不明だが、フランスのブドウ園の1/3から半分が全滅したといわれる。中でも最も悪い打撃を受けたのはブランデー生産の中心部、CognacとCharenteだった。UKのブランデーの飲み手は彼らのお気に入りの酒を探したが手に入れることができなかった。唯一、金持ちだけが法外な値段で手に入れることが出来た。
そのうちにフランスのブドウ園はフィロキセラに免疫のあるアメリカのブドウを植えたり接ぎ木したりして再生した。しかししばらくはブランデーは入手できなかった。そのため、UKのブランデーを飲むクラスはスコッチに切り替えた。
幸運にも、その頃モルトウィスキーの熟成にシェリー樽を使用するのが増えてきた。シェリーはその当時、UKで一般的な飲み物になっていた。シェリー酒はスペインから大きな樽でやって来るが空き樽をスペインに返すのは不可能だった。したがって、とても多くの質のよいシェリー樽が到着地の港で余っていた。ほとんどのスコッチ蒸留所は自身の樽を制作するためにクーパーを雇っていたけれども、倹約な蒸留業者はとてもよい掘り出し物としてそれらのシェリー樽を安く手に入れた。船や鉄道でスコットランドへ輸送された樽はスコッチ用に再生され、利用された。このようにして出来たシェリー樽熟成のウィスキーは熟成感があり、ブランデーを飲んでいた人々にも次第に受け入れられていった。数年後、ブランデーが市場に復活したが、スコッチウィスキーのシェアは落ちなかった。
同じ頃、工業の発展によりガラス瓶の大量生産が可能になった。現在ではガラス瓶は珍しくもなく、むしろペットボトルや缶に取って変わられようとしている。しかし19世紀の後期までは手ごろなサイズで高品質で耐久性のあるボトルは存在しなかった。手ふきで作られたのでサイズや形状が微妙に変化していた。また、多くは底部が丸く、何かの台がない限り立てられないものだった。
鋳型技術の発達は品質を高め、単価を下げた。大量の労働力を集中できるならば商品の瓶詰めが可能になった。しかしスコットランドでは現在もウィスキーの樽売りは残っている。
19世紀末のウィスキーブームの記録として、1887年に発表されたAlfred Barnardの"The Whisky Distilleries of the United Kingdom"がある。この本はジャーナリストであった著者がスコットランドを旅して、訪れた蒸留所を記録していったもので、1885年から蒸留所を訪れる旅に出ている。
19世紀末の10年間はUKにだいたい160のウィスキーを生産している蒸留所があった。スコットランドに129(キャンベルタウンだけで21を含む)、その時はまだUKの一部だったアイルランドに28、イングランドに4。そして1900年までの年に、24の蒸留所が建設されていた。
しかし、もし彼が40年後、同じ旅をしたなら荒れ果て、絶望したウィスキー業界を目にしただろう。
禁酒法と世界大恐慌
1890年代、UKは絶頂期にあった。UKの産業は世界の羨望だった。そして広大な地域を支配していた。
また、酒の安い国だった。パブやエールハウスで、1ジル(1/3パイント)のウィスキーの代金は4ペンスほど。当時のウィスキーは現在の標準的なアルコールの強さの40%よりも強かった。これはある点で問題だった。
多くの人々が貧困や悪い環境に直面していたその時代、飲酒は唯一の楽しみとなった。安くて強いアルコールに頼る人が多かった。
アルコール中毒が広まって、いくつかの地域では支配不能になった。その当時の地方紙を見ると、ただ単に酔っぱらいを扱う法廷の報告をすぐに見つけることが出来る。
20世紀になるまで教会や禁酒運動団体は、社会の諸悪の根元のように飲酒を標的にした。しかしそれはすべての交通事故の責任を自動車メーカーに負わせるようなもの。しかし多くの人々が社会の大きな荒廃の原因を酒を見なして疑わなかった。
1909年、当時の大蔵大臣だった David Lloyd George(後に首相となる) は突然、酒税の引き上げを行った。しかも今までにない、高い比率の課税だった。当然のことながら、酒の値段が上がり、消費は急激に落ち込んでいった。
Lloyd George の税金の引き上げは大衆をまじめにする効果があったとはいえ、消費の落ち込みによる減収のほうが、はるかに臨時歳入より多かった。しかしそれは素晴らしい先例とされ、1920年までの間に酒税は6倍に引き上げられた。
第一次世界大戦の勃発にともない、規制が行われた。
1914〜15年の冬期に軍需工場からの生産量はひどく遅れた。原因は主として原材料の不足と下手な現場管理だった。けれども、政府は飲酒を犯人と見なした。パブリックハウスの営業時間は徹底的に短縮させられた。昼食時の2〜3時間と夜の4時間ほど、そして最も遅くても22:00に閉店が標準となった。スピリッツの度数も急激に下げられた。特に軍事基地や軍需工場のまわりでは厳しかった。
しかし、それらの処置は戦争期間中の一時的なものだったが、パブの営業時間は最近までそれに近いものだった。
さらに、モルトウィスキー製造のための大麦の供給が制限された。戦争により、物資が不足するために仕方のない措置だった。しかしグレーンウィスキー蒸留業者の影響は少しだけにとどまった。工業用アルコールは製造業や溶剤の目的で大量に必要とされた。そしてフーゼル油はニスを製造したり飛行機のドープ塗料を作るのに必要とされた。
いくつかの蒸留所は20世紀の早い時期、後期ヴィクトリア朝時代の好景気からエドワード7世時代の不況に変わった時にすでに閉鎖されていた。1909年の増税の余波を受けてさらに閉鎖された。多くの生き残った蒸留所は戦争期間中、"mothballed(休止状態)"となった。
ウィスキー製造業者は戦争が終われば元に戻ると考えていた。しかし彼らの楽観論はひどく思い知らされることとなった。1920年代はウィスキー業界にとって最も暗黒の時代となった。
いくつかの要因は、1920年代の経済の急激な落ち込みの原因と同じだった。USの禁酒法は、ウィスキー産業の一番の輸出市場に打撃を与えた。スコッチは禁酒法の時代も"医療目的"や密輸業者経由でアメリカへ輸出されてはいたが、US市場の衰えは国内の売り上げによって相殺することはできなかった。ウィスキーはさらに課税された。
スコットランドでさえ、1920年12月に禁酒法の国民投票が開催された。国民は施行反対を決めたものの、国民投票が開かれたという事実がどのくらい強力な禁酒運動だったかを表している。
暗黒の時代は1926年のストライキ、1929年のウォール街の大暴落を過ぎて1930〜34年の世界大恐慌まで引きずられた。1930年代初期の記録では、スコットランドでたった8ヶ所の蒸留所しか操業していなかった。アイルランドではさらにひどく、28あった蒸留所が2つになっていた。
この危機を救ったのが当時のDCLの最高責任者、William Rossである。彼は、無数の蒸留所を買収して、閉鎖することによってこの危機を乗り切ろうとした。一種のリストラである。
いくつかは第二次世界大戦後の新しいウィスキーブームに再開するにしても、蒸留所閉鎖は彼の時代から始まった。閉鎖はスコットランドの隅々まで広まっていった。すべての中で最もひどい打撃を受けたのが、1920年代に21蒸留所中ほとんどすべての18蒸留所が閉鎖されたCampbeltownだった。ここの付加的な要因として、200年間安い石炭を蒸留所に供給していた、MachrihanishにあるDrumlemble炭坑の枯渇があった。その炭坑の閉鎖はさらにCampbeltownへ石炭を運搬していた軽便鉄道の廃止も決定的となった。
第二次世界大戦とその後
ウィスキー産業の好転のきっかけは経済が徐々に復活してきた時期の1934年、アメリカ大統領Franklin D.Rooseveltによる禁酒法の廃止だった。蒸留所は徐々に活気を取り戻し、1938年には、20世紀になってからの最高の生産量となった。
その直後に戦争が勃発。当初、スコッチウィスキーは物資や武器の購入のための重要な輸出品として、生産が強化された。しかしアメリカとの武器貸与協定が結ばれてウィスキーの必要性は下がった。逆に原料である大麦の使用に制限を受け、生産を縮小せざるをえなかった。1943年はすべての蒸留所が休止状態だった。1944年の終盤、ヨーロッパの戦いの終わりを感じさせる時期に、首相Sir Winston Churchillはウィスキーの生産の再開を促した。その結果、30程の蒸留所が1945年1月に操業を再開した。
戦後の経済復興の中、スコッチウィスキーは再び重要な輸出品となった。輸出を重視するあまり、国内流通が不足する事態も発生した。
そして、20世紀で初めての蒸留所建造計画がスタートした。1960年代に開業された蒸留所がそれである。
同時に20世紀初めに休止したままの蒸留所を再生する計画も進められた。
その後は順調に生産量、売上を伸ばしていた。その主役はブレンデッドウィスキーであったが、GlenGrantのイタリア市場への浸透、Glenfiddichの世界戦略とシングルモルトの知名度も上昇した。
しかし、スコッチウィスキーが売れたために発生する問題があった。輸入国の国内生産品を保護するために高い関税が課せられることである。この頃の日本では、円の価値が安かったこともあり、スコッチウィスキーは高級酒で小売価格はWhite HorseやDewar'sなどのスタンダードクラスは\3,600、Chivas Regalなどのプレミアムクラスは\10,000前後となっていた。Old Parrやジョニ黒がステータスシンボルだった時代である。
1980年代に入ると順調だったスコッチウィスキーに陰りが見え始めた。この頃になると蒸留所単独経営を行っているところは少なく、ほとんどの蒸留所は大手ウィスキー会社の系列となっていた。スコッチウィスキー業界に大打撃を与えるほどの落ち込みではなかったものの、1990年代初めにかけて20程の蒸留所が閉鎖や休止状態に追い込まれた。生産効率向上が目的と思われる。
けれども以前のような暗黒の時代ではない。スコッチウィスキーの見通しは決して暗いものではない。
日本の輸入ウィスキーに対する関税が引き下げられた後、スコッチウィスキーの差別的な課税はどの国にも見られない。重要な輸出品として、国がバックアップをしている。
また観光資源として、蒸留所は古城、stately homeと並んでスコットランドにやってくる観光客を集めている。多いところでは年間15万人が訪れる。
1980年代に閉鎖された蒸留所のいくつかは再開された。日本企業のバックアップや瓶詰め業者が買収して再開したところもある。そして1990年代に入って新しい蒸留所がわずかだが開業した。
日本では輸入ウィスキーに対する関税が引き下げられた後、非常に流通状況が改善され、スコッチウィスキーを以前より安く、そして数多くの種類を楽しむことができるようになった。着実にモルトウィスキーファンは増加している。ブームというには今一つ盛り上がりに欠けるがワインのような日本特有の「熱されやすく冷めやすい」状況よりは良いのでは、と思う。